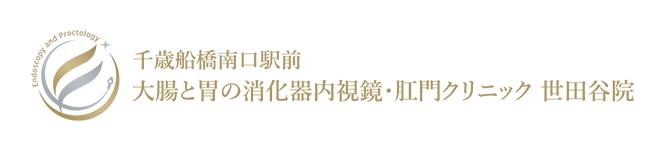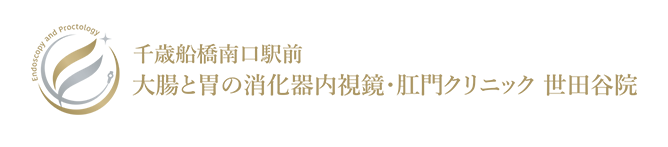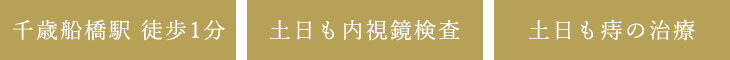おならが止まらない
 おならとは、肛門から出る気体のことで、飲食や緊張した際などに飲み込んだ空気と一緒に、大腸内の細菌が食物を分解した際に生じるガスが混ざって放出されます。誰しもおならが腸内に溜まりますが、疾患や食生活の影響でガスが増加して、おならがよく出るといった状態に陥ります。 膨満感やガスが溜まったように感じることは誰しもあることだと思います。これらの症状は、多くは腸内でガスが過剰発生することが原因で起こりますが、それ以外の原因も考えられます。おながらよく出る方は放置せずに、専門医に相談することをお勧めします。おならにお悩みの方は一度当院までご相談ください。
おならとは、肛門から出る気体のことで、飲食や緊張した際などに飲み込んだ空気と一緒に、大腸内の細菌が食物を分解した際に生じるガスが混ざって放出されます。誰しもおならが腸内に溜まりますが、疾患や食生活の影響でガスが増加して、おならがよく出るといった状態に陥ります。 膨満感やガスが溜まったように感じることは誰しもあることだと思います。これらの症状は、多くは腸内でガスが過剰発生することが原因で起こりますが、それ以外の原因も考えられます。おながらよく出る方は放置せずに、専門医に相談することをお勧めします。おならにお悩みの方は一度当院までご相談ください。
おならが止まらない原因
繊維質が多い食事
食物繊維は、胃や小腸で消化・吸収されずにそのまま大腸にまで届きます。食物繊維は、便量を増やして排便をスムーズにしたり、血糖値の上昇を緩やかにしたりなど、様々な働きがありますが、過剰に摂取した場合、腸内でガスが発生しやすくなり、おならが出やすくなります。食物繊維は「第6の栄養素」とも呼ばれるほど大切な栄養素のため、十分な量を摂ることが勧められますが、おならが頻発する場合は摂取量をコントロールしましょう。
肉類やにんにくの食べ過ぎ
肉類を過剰摂取すると、小腸で吸収できなかった分が大腸に到達して分解されます。腸内の悪玉菌によって分解されると腐敗し、硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、インドール、スカトールなどくさいおならが出るようになります。また、硫黄分が豊富なにんにくなどを食べ過ぎた場合も、くさいおならが出ることがあります。
便秘
便秘により大腸内に便が溜まった状態で、便が発酵・腐敗してガスが大量に発生し、おならが頻発しやすくなります。また、悪玉菌の働きにより、おならのにおいもくさくなります。
腸内に溜まったガスが腸から吸収され、硫化水素や二酸化硫黄、アンモニアなど毒性の物質が血流にのって全身に運ばれると、体調不良や肌荒れになる可能性もあります。
ストレス
緊張やストレスを受けた際に、息を呑む回数が増加して、吸い込む空気量が増加します。体内の空気量が多くなるため、ガスも発生しやすくなります。
女性特有の原因
女性の方でおならが止まらないとお悩みの場合、女性ホルモンの分泌や子宮の収縮が関与している可能性があります。
更年期になると女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少し、自律神経のバランスが崩れることで、おならが頻発することがあります。また、生理前は黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が増加しますが、このホルモンは腸の蠕動運動を抑える働きがあり、腹部の張りや、くさいおならの原因となります。
食事の仕方
 早食いや咀嚼回数が少ないなどの食べ方は唾液の分泌量が減少し、吸い込む空気の量が増えるため、ガスが発生しやすくなります。また、噛まないために食物がそのまま胃に運ばれるため、消化に時間がかかって腐敗が発生し、強いにおいのあるおならが出るようになります。
早食いや咀嚼回数が少ないなどの食べ方は唾液の分泌量が減少し、吸い込む空気の量が増えるため、ガスが発生しやすくなります。また、噛まないために食物がそのまま胃に運ばれるため、消化に時間がかかって腐敗が発生し、強いにおいのあるおならが出るようになります。
おならが止まらない時に
考えられる疾患
おならが増える疾患は様々なものがあります。過敏性腸症候群の下痢型、あるいは便秘と下痢が繰り返し起こる混合型では、ガスが溜まりやすく、おならが増えます。また、大腸がんは便秘の原因となることや慢性胃炎では胃の機能が低下して消化不良が起こることで、おならが増えることがあります。
慢性胃炎
ピロリ菌感染による慢性胃炎によって、胃の運動機能が低下し、胃の内容物が停滞します。主な症状は胸焼けや胃痛、吐き気、胃の運動機能の低下によるげっぷやおならなどが挙げられます。
過敏性腸症候群
下痢、便秘、腹痛といった症状が慢性化しているにも関わらず、大腸カメラ検査では異常を認めない状態です。 原因は明らかになっていませんが、不安や緊張といった精神的ストレス、睡眠不足、疲労、不規則な食生活などの身体的ストレスなどが複合することによって、腸の蠕動運動に異常が起こり下痢や便秘などの症状が起こると考えられています。腹痛に伴って下痢を繰り返す「下痢型」、便秘を繰り返す「便秘型」、下痢と便秘が繰り返し起こる「混合型」、いずれのタイプにも当てはまらない「分類不能型」の4つに大別されます。
このうち、便秘型や混合型では、便が腸内に留まることで、腸内で発酵・腐敗が起こり、おならが増えることがあります。また、分類不能型では膨満感やおならなどの症状が続き、生活に大きな支障を及ぼすことがあります。原因ははっきりとしていませんが、腸の蠕動運動や知覚の異常が関係しているのではないかと言われています。
大腸がん
大腸がんは早期では自覚症状が乏しく、定期的に大腸カメラ検査を受けていないと早期発見が困難です。がんが進行すると、腸管が狭窄して便秘、排便困難になります。このため、便が腸内に長時間留まるようになり、おならが頻発するようになります。この場合、おならの音も小さくなる傾向があります。
呑気症(空気嚥下症)
食事の際に気づかないうちに空気を吸い込んでいますが、空気の大部分は窒素であるため体内では吸収されず、げっぷの際に口から外に出ます。出しきれなかった空気が、食べ物と一緒に大腸にまで到達し、腸で発生したガスと混ざっておならとなります。
呑気症は、空気を吸い込む量が多くなり、げっぷやおならの量が増える疾患です。暴飲暴食、早食いなどが習慣化している人、口呼吸をしている人が発症しやすいと言われています。また、ストレス耐性が低い方も、気づかないうちに多くの空気を飲み込んでいるため、呑気症を発症しやすいと考えられています。
おならの予防
肉類を食べ過ぎないようにする
硫黄成分が豊富なタマネギやニンニクなどの野菜、肉類などを食べ過ぎた場合、大腸でウェルシュ菌などの悪玉菌によって分解され、腐敗・発酵が進んで強いにおいのガスが発生します。悪玉菌の増加を抑え腸内の細菌叢のバランスを整える必要があります。乳酸菌を含むヨーグルトなどを積極的に食べて、悪玉菌の増加を抑え腸内の細菌叢のバランスを整えましょう。また、ぬか漬けなどの酪酸菌が豊富な食べ物、サプリメントなどもお勧めです。
便秘を改善する
便秘は大腸に便が溜まってしまうため、便が発酵・腐敗してガスが大量に発生し、おならが増えます。便秘を予防するために生活習慣を整えることはおならのにおいや量を抑えることにも繋がります。以下を意識してみましょう。
- 水分をしっかり摂取する
- 適度な運動習慣
- 食物繊維が豊富な食品を摂取する
- 便意を催したら我慢しない
おならや便意を我慢すると直腸の感度が低下し、便意を感じなくなり便秘の悪化を来します。おならは、人前では羞恥心から我慢しがちですが、便秘の悪化を防ぐためにも、便意やおならを感じたらすぐにトイレに行きましょう。
運動は、無理のない範囲で軽い有酸素運動を習慣化することが大切です。毎日ではなくとも、2日に1日でも十分です。
食事では、食物繊維を摂ることで便秘の改善が期待できます。食物繊維は、豆類やイモ類、野菜、穀類などに豊富に含まれています。
その他、腸内細菌叢を整えるために、ヨーグルトや乳酸飲料、オリゴ糖を豊富に含む食品などを食べましょう。オリゴ糖が豊富な食品には、バナナやはちみつ、きな粉、納豆、インゲンなどが挙げられます。
ストレス解消
ストレスによって身体の様々な場所に悪影響が及びますが、胃腸も例外ではありません。ストレスによって過敏性腸症候群の発症に繋がるとも言われています。
人前でおならをしないと我慢していると、よりストレスが溜まります。ストレスを溜めないように、旅行や趣味、スポーツなど、ご自身がリラックスできる時間を作りましょう。
おならが止まらない方は
ご相談ください
 ストレスによって身体の様々な場所に悪影響が及びますが、胃腸も例外ではありません。ストレスによって過敏性腸症候群の発症に繋がるとも言われています。
ストレスによって身体の様々な場所に悪影響が及びますが、胃腸も例外ではありません。ストレスによって過敏性腸症候群の発症に繋がるとも言われています。
人前でおならをしないと我慢していると、よりストレスが溜まります。ストレスを溜めないように、旅行や趣味、スポーツなど、ご自身がリラックスできる時間を作りましょう。