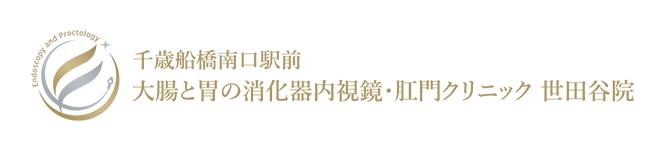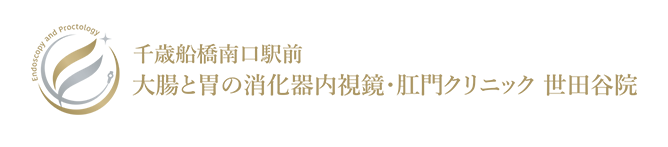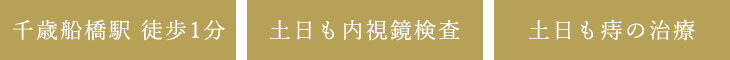胃もたれの原因
胃は、食べ物を一時的にためて消化を開始する臓器です。ここでは胃酸や消化酵素が分泌され、食べ物が分解されるとともに、食べ物を粥状にして小腸へ送り、栄養が効率よく吸収されるように整えます。胃もたれとは、消化機能が低下して、食べ物が胃の内部に留まることで不快感を覚える状態です。普段から多くの方が経験する症状で、以下のような原因で起こることが多いです。
食べ過ぎ・飲みすぎ
揚げ物や高脂肪な食品など、消化しにくい食べ物は胃の負担となります。また、食事時間が不規則になっている、栄養バランスが乱れている、食後すぐに横になるといった生活習慣も、胃の負担になります。こうした要因が組み合わさって胃酸が必要以上に多く分泌されると胃もたれが起こります。
ストレス
 消化管は自律神経によって制御されています。過労やストレスによりこの自律神経のバランスが崩れると、胃の運動機能が低下し、胃液の分泌量も少なくなります。これにより、消化不良が起こり、胃の中で食べ物が留まってしまうことで胃もたれが発生します。
消化管は自律神経によって制御されています。過労やストレスによりこの自律神経のバランスが崩れると、胃の運動機能が低下し、胃液の分泌量も少なくなります。これにより、消化不良が起こり、胃の中で食べ物が留まってしまうことで胃もたれが発生します。
加齢
加齢に伴って胃の運動機能が低下することで胃もたれが発生します。
胃もたれの原因となる病気
機能性ディスペプシア
慢性的な胃痛や胃もたれ、お腹の張り、すぐに満腹になるなどの症状があるのに、胃カメラ検査で胃の粘膜を調べても問題がみつからない疾患です。原因が分からないお腹の不調にお悩みの方は、一度当院にご相談ください。
胃下垂
胃を支える筋肉が少なくなることで、胃が本来の位置よりも垂れ下がった状態です。胃機能が弱まるため、胃もたれが発生しやすくなります。
胃がん
日本人は胃がんの発症率が高く、年間で10万人以上の方が胃がんを発症しています。初期では自覚症状が乏しいことが多く、進行しても症状が現れないこともあります。胃もたれ、胃痛、食欲不振、吐き気、げっぷなどが主な症状です。胃がんは早期発見すれば十分に根治が期待できる疾患です。継続的に胃痛などの症状を認める場合は、早めに胃カメラ検査を受けましょう。
肝臓・膵臓・胆のうなどのがん
肝臓・膵臓・胆のうに発生したがんが悪化すると、胃の圧迫感や胃痛、胃もたれが起こることがあります。また、黄疸が現れることもあります。肝臓・膵臓・胆のうに発生したがんは、腹部超音波検査やCT検査、MRI検査により発見できます。
※CT・MRI検査が必要な場合は連携先の医療機関をご紹介します。
胃もたれの検査・診断
胃もたれが起きている場合、まずは問診にて、症状の程度や起こるタイミング、生活習慣、既往歴などについて丁寧にお伺いします。その後、必要に応じて以下のような検査を実施します。
胃カメラ検査
 胃もたれがある場合、胃カメラ検査が有効です。実際に食道、胃、十二指腸に原因があるかすぐにわかります。内視鏡は鼻または口から挿入しますが、患者様に選んで頂けます。検査には鎮静剤を用いるため、ウトウト眠ったような状態となり、不快感や苦痛を最小限に抑えられます。検査中に病変が見つかった場合、そのまま組織を採取して病理検査を行い、確定診断します。
胃もたれがある場合、胃カメラ検査が有効です。実際に食道、胃、十二指腸に原因があるかすぐにわかります。内視鏡は鼻または口から挿入しますが、患者様に選んで頂けます。検査には鎮静剤を用いるため、ウトウト眠ったような状態となり、不快感や苦痛を最小限に抑えられます。検査中に病変が見つかった場合、そのまま組織を採取して病理検査を行い、確定診断します。
腹部超音波検査
 胃もたれ原因を超音波検査で確認します。肝臓、膵臓、胆のう、腎臓などを検査できます。
胃もたれ原因を超音波検査で確認します。肝臓、膵臓、胆のう、腎臓などを検査できます。
胃もたれの治し方
生活習慣の改善
食習慣や運動習慣など生活習慣の改善により、胃もたれの解消が見込めます。食生活では、刺激物や高脂肪食は避け、腹八分目に抑えましょう。また、食事はゆっくりよく噛んで食べるように意識してください。食後すぐに横になると胃もたれが起こりやすいので、食後から少なくとも2時間経過してから横になりましょう。
適度な運動を習慣化し、胃への血流を促すことも胃もたれの解消に繋がります。ストレッチやウォーキングなど、普段の生活でも続けられそうなものから取り組んでみましょう。
ストレスを溜めない
身体的な負担やストレスで、胃の運動機能が低下して、胃もたれが起こります。無理なく行えるストレス発散法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
十分な睡眠
十分な睡眠時間の確保と睡眠の質を高めることで、身体の疲労が取れ、自律神経のバランスが整います。睡眠が足りないと、疲労が溜まり、自律神経の乱れにも繋がり、胃もたれを招いてしまいます。良質な睡眠をとれるように工夫してみましょう。
胃もたれの症状は当院へ
 当院では、胃もたれだけでなく、腹部膨満感や胃痛、呑酸(酸っぱいげっぷ)など、様々な消化器症状の治療を行っています。患者様の症状をお伺いした上で、必要に応じて胃カメラ検査や大腸カメラ検査、腹部超音波検査などを行い、原因に応じた適切な治療を実施します。胃もたれでお困りの方は、一度当院までご相談ください。
当院では、胃もたれだけでなく、腹部膨満感や胃痛、呑酸(酸っぱいげっぷ)など、様々な消化器症状の治療を行っています。患者様の症状をお伺いした上で、必要に応じて胃カメラ検査や大腸カメラ検査、腹部超音波検査などを行い、原因に応じた適切な治療を実施します。胃もたれでお困りの方は、一度当院までご相談ください。