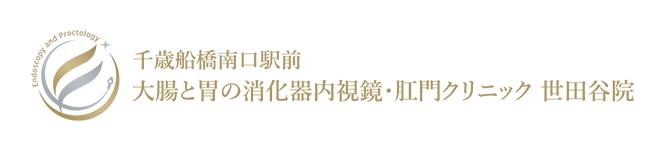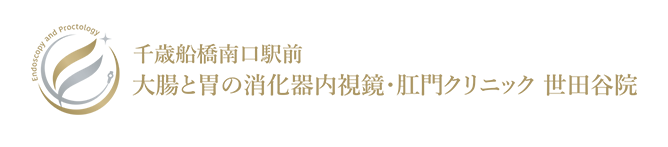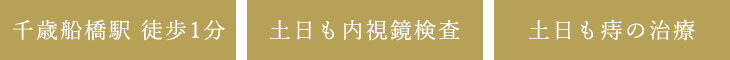胸焼けについて
 胃酸がこみ上げる感覚や胸が焼けるような感覚、ヒリヒリするような痛みを感じる状態を胸焼けといいます。多くは、胃酸が逆流することで食道粘膜がダメージを受けることによるものです。食後の満腹状態で胃が膨れ上がり、食道と胃のつなぎ目部分の下部食道括約筋が弛緩することで生じます。加齢や肥満が原因となり、他にも食道の蠕動運動の機能低下、食道粘膜の知覚過敏も影響すると言われています。 胸焼けの感じ方は個人差があり、胸のつかえ感、胸痛、背中の張り、呑酸などの症状が起こると考えられます。胸焼けでお困りの方は一度、当院までご相談ください。
胃酸がこみ上げる感覚や胸が焼けるような感覚、ヒリヒリするような痛みを感じる状態を胸焼けといいます。多くは、胃酸が逆流することで食道粘膜がダメージを受けることによるものです。食後の満腹状態で胃が膨れ上がり、食道と胃のつなぎ目部分の下部食道括約筋が弛緩することで生じます。加齢や肥満が原因となり、他にも食道の蠕動運動の機能低下、食道粘膜の知覚過敏も影響すると言われています。 胸焼けの感じ方は個人差があり、胸のつかえ感、胸痛、背中の張り、呑酸などの症状が起こると考えられます。胸焼けでお困りの方は一度、当院までご相談ください。
以下のような胸焼けの
症状はありませんか?
- 胸がつかえる感覚がある
- 胸に違和感や不快感を覚える
- 胸が熱い感覚がある
- 咳がとまらない
- 酸っぱいげっぷが出る(呑酸)
- 起床時に口の中に不快感がある
- 背中が張る
- 胃が張る
- みぞおちあたりに痛みがある
- げっぷが多い
など
受診の目安
受診すべき症状
以下のような胸焼け症状がある場合、当院をご受診ください。
- 胸焼けが慢性化している
- 食べると胸が痛い
- みぞおちあたりも痛い
- 内服しても胸焼けが解消しない
- 内服で症状が一時的に治まるが、時間が経つと現れる
胸焼けの原因
暴飲暴食
暴飲暴食や、食後すぐに横になることは胃腸に負担がかかり、胸焼けの原因となります。胸焼けのある時は、消化の良いもをを食べましょう。
刺激物・高脂肪分の過剰摂取
酸味がある食品や香辛料などの刺激物、肉や揚げ物といった脂っこいもの食べ過ぎは胸焼けを起こします。刺激物や高脂肪食の食べ過ぎに注意です。
胃の圧迫
肥満や便秘、妊娠などにより胃が下から圧迫されると胸焼けが起こります。適量の食事と、適度な運動習慣を意識しましょう。食後は胃の内容物が多いため、就寝の約3時間前までに夕食を済ませましょう。
喫煙
喫煙は食道と胃の繋ぐ括約筋を緩め、胃酸の逆流を来し、胸焼けが起こります。
ストレス
ストレスによって、胃の運動機能が低下し、胃の内容物が停滞するため、逆流しやすくなり胸焼けが起こります。良質な睡眠を十分に取り、リラックスできる時間を設け、心身の健康を維持しましょう。
胸焼けで考えられる疾患
逆流性食道炎
ストレスによって、胃の運動機能が低下し、胃の内容物が停滞するため、逆流しやすくなり胸焼けが起こります。良質な睡眠を十分に取り、リラックスできる時間を設け、心身の健康を維持しましょう。
非びらん性胃食道逆流症
内視鏡検査を行っても食道粘膜に炎症が認められないにもかかわらず、逆流性食道炎と同様に胸焼けや胸痛、胃の不快感などの逆流症状を示します。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸の粘膜が深く損傷を受けた状態です。これが消化管の働きを妨げ、胃に内容が停滞し、胸焼けの原因となります。原因には、ピロリ菌感染やストレス、鎮痛剤やステロイドの副作用などが挙げられます。
食道がん
食道粘膜に発生するがんで、飲酒や喫煙習慣がある方はリスクが高いです。胸焼けや食事に伴う胸の痛みが起こります。早期発見・早期治療により根治が望める疾患であり、症状のある方は当院へご相談ください。
胸焼けの検査
胸焼けの原因が消化器疾患の可能性があるなど、医師が必要と判断した場合には、下記の検査をおこない、より正確な診断をします。
胃カメラ検査
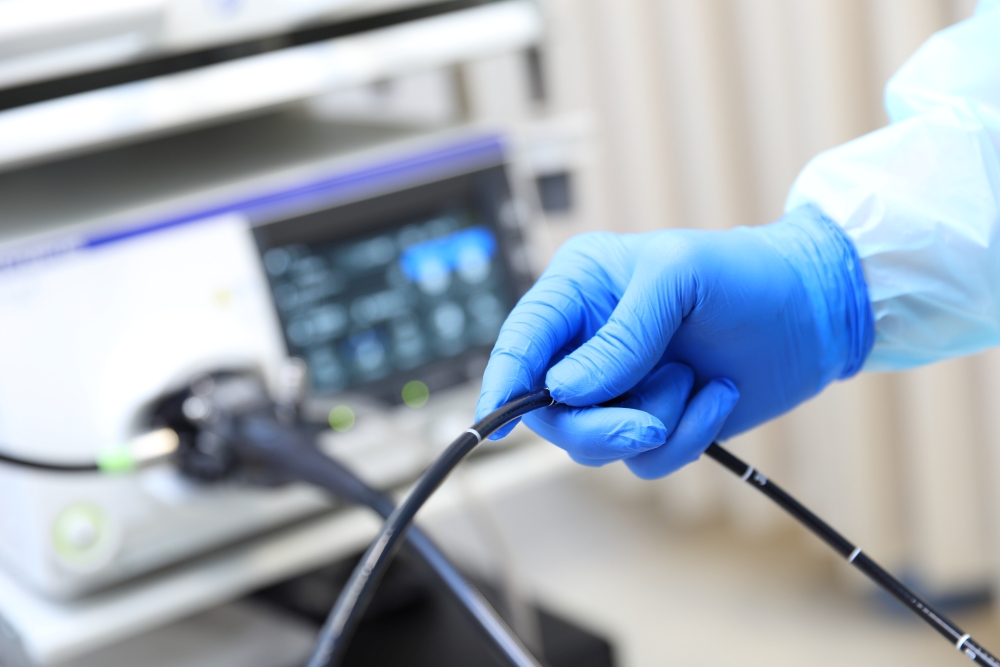 胸焼けがある場合、胃カメラ検査が有効です。実際に食道、胃、十二指腸に原因があるかすぐにわかります。内視鏡は鼻または口から挿入しますが、患者様に選んで頂けます。検査には鎮静剤を用いるため、ウトウト眠ったような状態となり、不快感や苦痛を最小限に抑えられます。検査中に病変が見つかった場合、そのまま組織を採取して病理検査を行い、確定診断します。
胸焼けがある場合、胃カメラ検査が有効です。実際に食道、胃、十二指腸に原因があるかすぐにわかります。内視鏡は鼻または口から挿入しますが、患者様に選んで頂けます。検査には鎮静剤を用いるため、ウトウト眠ったような状態となり、不快感や苦痛を最小限に抑えられます。検査中に病変が見つかった場合、そのまま組織を採取して病理検査を行い、確定診断します。
胸焼けの治し方・予防
胸焼けの解消・予防には、食生活の見直しや禁酒・禁煙、ストレス解消など生活習慣の改善が必要です。
食生活の見直し
早食いや暴飲暴食は胸焼けの原因となります。また、肥満や妊娠などにより腹圧が上昇すると、胃酸の逆流が起こりやすくなります。食事では、肉類や脂肪の多い食、炭酸飲料、アルコール、コーヒー、チョコレート、柑橘類などは胃酸の逆流が起こりやすくなるため、摂りすぎに注意しましょう。
禁煙
喫煙は、食道と胃の繋ぎ目の括約筋を弛緩させ、胃酸の逆流リスクが高まります。理想は禁煙ですが、難しい場合は、徐々に減らしていきましょう。
正しい姿勢
腹部を圧迫するような服装は、腹圧が高まるため逆流しやすくなります。また、猫背や就寝中の姿勢にも注意が必要です。右側臥位で寝ると下部食道括約筋が弛緩するため、逆流リスクが高まるため、左側臥位で頭の位置を高めにして寝るようにしましょう。
服薬における注意点
お薬を飲んでいる場合、十分な量の水も一緒に飲みましょう。水分が少ないと、食道粘膜にお薬が付着して、胃酸の逆流の原因となります。