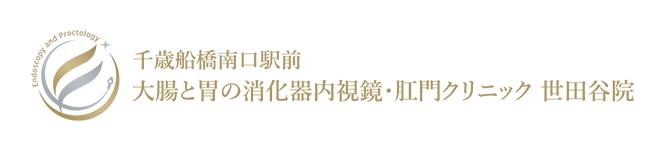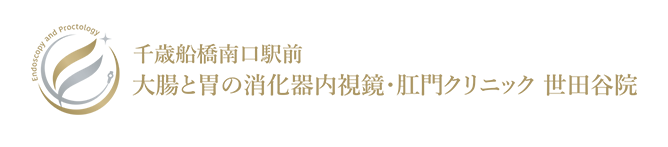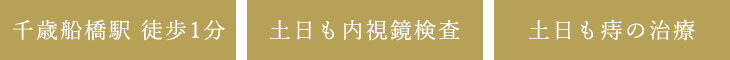下痢について
 水のような便や形を保てないほど軟らかい便など、水分量の多い便が頻回に排出される状態です。腹痛や血便を伴うこともあります。お腹の冷えや暴飲暴食などが原因の一時的なものもありますが、消化器疾患の症状として出ている可能性もあります。下痢が長期間続く、繰り返し起こる場合は何らかの疾患の症状として起きていることも考えられます。潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどの深刻な疾患が原因となることもあります。軽い下痢でも慢性化している場合は、消化器内科で原因を検査することをお勧めします。
水のような便や形を保てないほど軟らかい便など、水分量の多い便が頻回に排出される状態です。腹痛や血便を伴うこともあります。お腹の冷えや暴飲暴食などが原因の一時的なものもありますが、消化器疾患の症状として出ている可能性もあります。下痢が長期間続く、繰り返し起こる場合は何らかの疾患の症状として起きていることも考えられます。潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどの深刻な疾患が原因となることもあります。軽い下痢でも慢性化している場合は、消化器内科で原因を検査することをお勧めします。
また、頻回の下痢は脱水を招く恐れがあるため、水分を十分に摂れていない場合はすぐに医療機関を受診してください。
このような下痢は受診が必要です
- 激しい下痢
- 強い腹痛がある
- 排便後も腹痛が治まらない
- 血便を伴う
- 吐き気や嘔吐を伴う
- 脱水症状を認める(のどが渇く、尿が少ない、出ない、濃い)
下痢は、日常的なお腹の症状であるため放置されることが多いですが、重篤な疾患の症状のひとつであることも考えられます。原因の分からない下痢が続いている方は、重篤化する前に専門医療機関を受診しましょう。
下痢の種類
下痢は、一時的に起きる急性下痢と、1ヶ月以上続く慢性下痢に分類され、さらに以下のように細分化されます。
急性下痢
浸透圧性下痢
油っこいものや過剰な飲酒により腸に大きな負担がかかり、吸収機能が弱まることで便中の水分量が増加して発症する下痢です。
分泌性下痢
食中毒、感染性腸炎、食物アレルギー、お薬の副作用などにより腸の粘膜がダメージを受け、分泌液が過剰になって発症する下痢です。
慢性下痢
蠕動運動性下痢
消化管の内容物を送り出す蠕動運動が亢進し、水分をしっかりと吸収できていない状態で便が排泄されることで生じる下痢です。
滲出性下痢
腸の炎症により、血液や細胞内の滲出液が粘膜から腸管内に浸み出す、または
水分吸収機能が低下することで便の水分量が増え、下痢になります。潰瘍性大腸炎やクローン病が原因となります。
下痢症状を起こす疾患
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
腸粘膜に慢性的な炎症が起こり、腹痛や下痢、血便などの症状が起こる疾患です。症状が起こる活動期と治まる寛解期を繰り返す特徴があります。炎症が悪化すると、重篤な合併症に繋がったり、大腸がんが発生しやすくなったりするため、症状が治まる寛解期も専門医の管理のもと治療を継続することが不可欠です。完治させる治療法がないことから難病指定を受けていますが、適切な治療により炎症をコントロールできれば、寛解期の状態を長く保てます。
大腸がん
大腸がんの発症初期は症状がほとんど現れませんが、進行に伴ってがんが大きくなると、腸管が狭窄し、下痢や便秘の頻発、血便などの症状が起こることがあります。
過敏性腸症候群(IBS)
検査を行っても器質的異常が発見されないにもかかわらず、腹痛とともに便秘や下痢が慢性的に起こる疾患です。ガスが増加することで膨満感などの症状が起こることもあります。消化管は自律神経によって制御されていますが、ストレスなどにより自律神経が失調し、消化管の知覚過敏や機能不全が起こることで発症するのではないかと言われています。
感染性胃腸炎
感染性腸炎の原因菌は様々ですが、深刻な症状が起こるリスクが高いのは病原性大腸菌やノロウイルスです。激しい下痢や嘔吐を示しますが、これら症状により体内で繁殖した病原体や病原体が生み出す毒素が体外に排泄されます。そのため、下痢止めや吐き気止めを服用してしまうと、病原体や毒素が排泄されず深刻な症状が発生するため、服用はお控えください。
下痢の検査・診断
問診にて体調や症状、便の状態などについてお聞きし、必要に応じて大腸カメラ検査、血液検査、便の培養検査などを行います。
大腸カメラ検査
 まずは問診にて体調や症状などについてお聞きし、必要に応じて大腸カメラ検査や腹部超音波検査、血液検査などを行います。
まずは問診にて体調や症状などについてお聞きし、必要に応じて大腸カメラ検査や腹部超音波検査、血液検査などを行います。
大腸カメラ検査は大腸粘膜の状態をリアルタイムで観察でき、怪しい病変があれば組織を採取して病理検査に回すことで、様々な疾患の確定診断に繋げられます。特に、大腸がんを早期の段階で発見できるのは大腸カメラ検査のみです。当院では、熟練の専門医が検査を担当し、高性能な内視鏡システムを駆使して正確な検査を行います。大腸カメラ検査では鎮静剤を使用することも可能で、ウトウト眠ったような状態で検査を受けて頂けます。
腹部超音波検査は、大腸カメラ検査では確認が難しい肝臓や膵臓、胆のう、腎臓の状態を確認できます。
血液検査では、炎症や貧血の有無、その程度を調べられます。
当院では、問診やこれら検査の結果をもとに総合的に診断を下し、原因や状態に応じた適切な治療を提供しています。
血液検査・便培養検査
血液検査では、炎症の程度を調べ、疾患の推定に役立ちます。
血便を伴う下痢など感染性腸炎で原因菌の特定が必要と判断される場合は便培養検査を行います。
当院では、問診やこれら検査の結果をもとに総合的に判断し、個々の原因や状態に応じた適切な治療を提供致します。
下痢の治し方・注意点
食事
絶食や消化しやすいものを少しだけ食べることをお勧めします。ただし、下痢は脱水症状を起こしやすいので、水分は可能な範囲で摂取して下さい。消化の悪い高脂肪食や食物繊維は控えて、できるだけ軟らかい食事にしましょう。おかゆ、うどん、湯豆腐などをお勧めします。また、下痢が改善してもしばらくは消化のよいものをとり、食べ過ぎないようにしてください。
胃酸の分泌を促すような食品も避けることが重要です。唐辛子・カフェイン・アルコールなど刺激の強いもの、高脂肪食、柑橘類などは控えましょう。また、味の濃いものもとり過ぎないようにしてください。
水分と電解質の補給
 頻回の下痢は電解質異常や脱水症状を起こす可能性があります。そのため、スポーツ飲料や経口補水液をこまめに飲むようにしましょう。下痢に伴って嘔吐も起こり水分補給がままならない場合、早めに当院までご相談ください。
頻回の下痢は電解質異常や脱水症状を起こす可能性があります。そのため、スポーツ飲料や経口補水液をこまめに飲むようにしましょう。下痢に伴って嘔吐も起こり水分補給がままならない場合、早めに当院までご相談ください。
市販の下痢止め服用は危険なことも
感染が原因である下痢(食中毒や感染性腸炎)の場合、体内で繁殖した病原体や病原体が生み出す毒素を体外に排泄するために下痢になります。そのため、下痢止めを服用すると、病原体や毒素が排泄されず重症化する可能性があります。感染の可能性がある場合、下痢止めの服用は控え、当院までご相談ください。
長期間下痢が続く方は当院へ
 下痢症状が長期間にわたって続く場合、何らかの疾患が原因である可能性もあります。急性の下痢は1週間以内には収まります。1週間以上、下痢が続く方で内視鏡検査や消化器内科の診察を受けていない場合は、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどすぐに治療が必要な疾患である可能性もありますので、原因を特定するためにも早めに当院までご相談ください。
下痢症状が長期間にわたって続く場合、何らかの疾患が原因である可能性もあります。急性の下痢は1週間以内には収まります。1週間以上、下痢が続く方で内視鏡検査や消化器内科の診察を受けていない場合は、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどすぐに治療が必要な疾患である可能性もありますので、原因を特定するためにも早めに当院までご相談ください。